【本当にあった不動産取引の怖い話】私道の通行権トラブル
不動産購入は人生の大きな決断です。とくに中古戸建や中古マンションなど、既存の物件を購入する際には、価格や立地だけでなく「権利関係」の確認が非常に重要です。今回は岡崎・西三河エリアで実際に起きた、私道の通行権トラブルを題材に、注意すべき点を詳しく解説します。
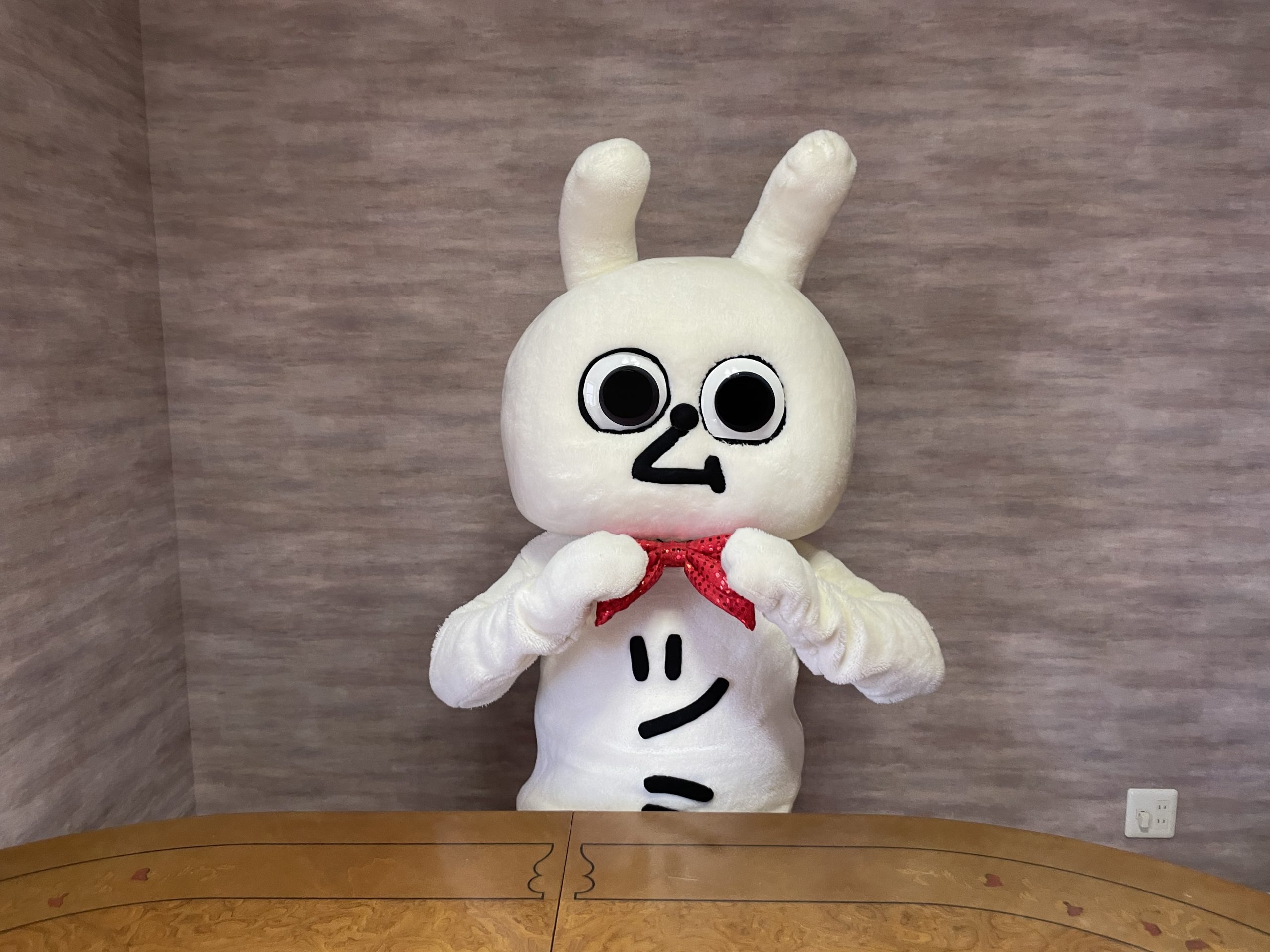
▼ムツミンが1分動画で分かりやすく解説▼
なぜ私道トラブルは起こるのか?
住宅街では、公道に直接接していない土地にアクセスするために「私道」が設けられているケースがあります。
このような場合、土地の所有者が単独で自由に利用できるわけではなく、共有持分や通行地役権といった権利関係が生じます。場合によっては、敷地の地下に隣家の上水道やガス管が埋設されていることも。
つまり「自分の土地」だと思っていた部分に、他人が通行できる正当な権利が残っていることがあるのです。
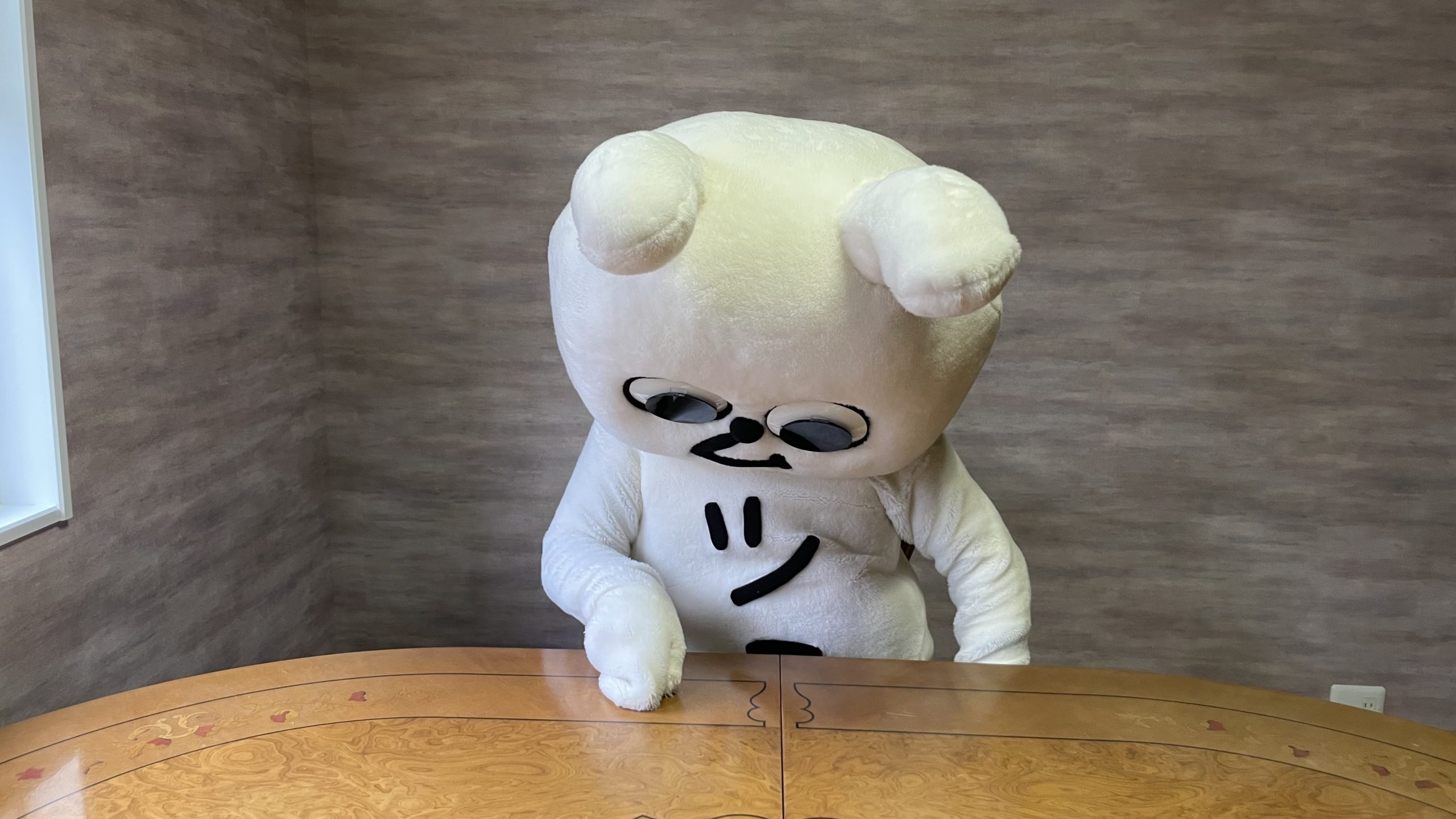
よくある原因
- 契約時の重要事項説明で「通行地役権」の説明が不十分、または買主の理解不足
- 登記簿や測量図に表記があっても、買主が見落としていた
- 共有持分の範囲や権利関係の確認不足や売主からの告知忘れ
- 境界確認を曖昧にしたまま契約してしまった
特に岡崎や西三河エリアでは、戦後の区画整理や相続で土地が細分化され、隣地境界線や境界トラブルが発生するケースが少なくありません。
トラブルを防ぐためには?
私道や共有地に関するトラブルを避けるために、購入前に以下を徹底しましょう。
- 契約前に必ず確認すること:「敷地内の私道」「共有持分」「通行地役権」「地中配管」「覚書」の有無
- 測量図・公図・登記簿謄本を入手し、見慣れない文言がないかチェック
- 宅建士による重要事項説明をしっかり聞き、わからない部分は質問する
- 隣地所有者との境界立ち会いを行い、不動産共有や通行権の有無を確認
これらを確認せずに契約を進めると、後々「知らなかったでは済まされない」隣地トラブルにつながりかねません。
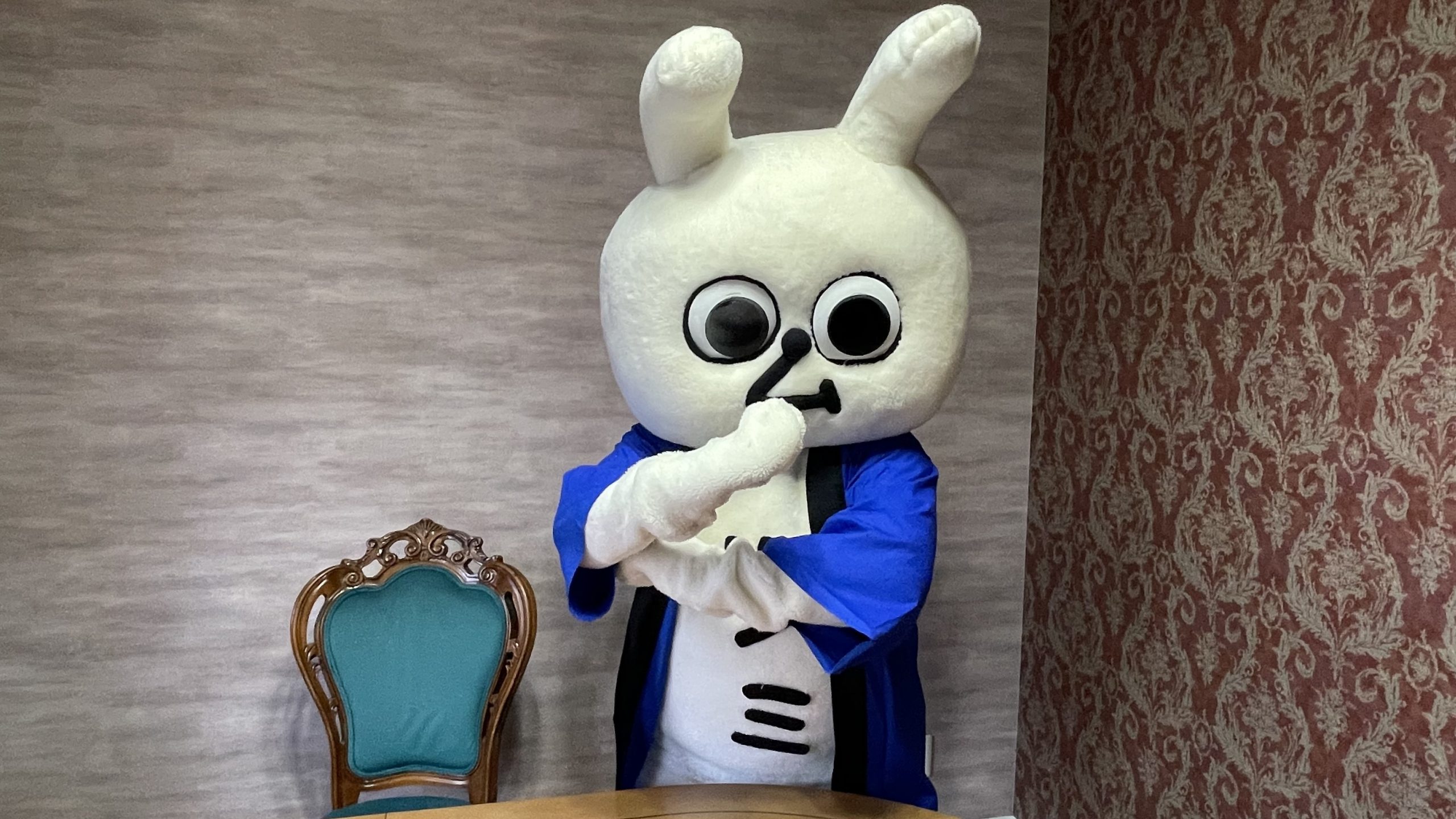
まとめ:岡崎・西三河で中古物件購入を検討する方へ
中古戸建や中古マンションを購入する際、物件の価格やリフォーム状態だけに注目してしまうのは危険です。特に「私道」「境界線」「不動産共有」といった権利関係は、不動産仲介のプロでないと見落としがちです。
岡崎市や西三河エリアは、土地利用の歴史が複雑で、境界トラブルや通行権問題が表面化するケースが少なくありません。
不動産仲介のムツミでは、登記簿・私道・地役権などの権利関係まで丁寧に確認し、契約不適合リスクを回避するサポートを行っています。
「中古物件を安心して購入したい」「相続不動産の売却で境界トラブルが心配」といった方は、ぜひご相談ください。
🏡 岡崎市・西三河エリアでの不動産購入・売却は、不動産仲介のムツミへ。